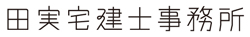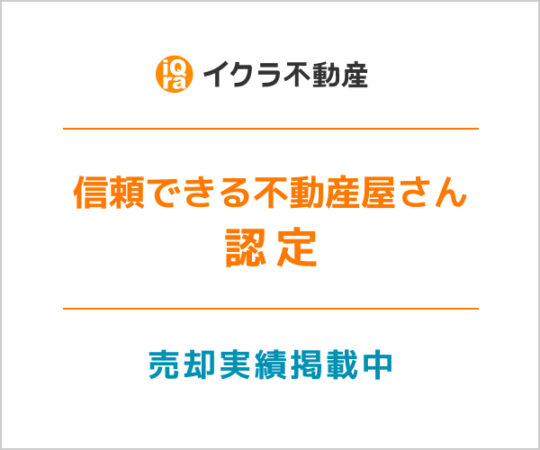前回の配信で不動産はひとつとして同じものがないことに触れました。中には似たものもありますが、それでも周辺環境・採光面・窓からの景色…など個別要素を含めていけば、同じものはないものです。
ふたつとないものですが、最終的には他の物件との優劣で、高い安いを判断されるという側面もこれまた現実であります。
分厚い査定書で理屈をつけて、価格の妥当性を展開しますが、他より魅力が薄ければ、評価されないのは致し方ありません。それが購入サイドの判断です。
難しいことは置いといて、やはり周辺より高く売却させるには、秀でる”なにか”が必要です。
いやいや私の物件は、、、とは思わず、”なにか”を感じて、PRするのが売却を預かる不動産会社の役目であります。
その点で、なにかを印象づけてよく魅せるには「物件写真」が大切であることは、言うまでもありません。
次に、外部環境です。他との優劣で価格が上下するものですから、言い換えれば他の物件が高ければ、高く売却できるタイミングということ。
相場が上がっている時期かどうか、周りの物件も現に強気設定で売りに出いるか、この2点が揃えば環境は揃っているといえます。
最後に販売期間について。売却を預かる不動産業者が、業績に追われていれば早くに売りたいでしょうから、価格改定を早い段階で切り出すでしょう。
売却成功を期すのに、焦りは禁物です。媒介契約は3ヶ月がひとつのタームのため、その期間中の売却と考える節がどこかムードとしてありますが、3ヶ月で売却できれば早い方。半年くらいを最低期間と思って望む姿勢が大切です。
なぜなら、時間の経過とともに、様々な事情で引越し先を探す購入検討者も新たに増えますので、3ヶ月間売れなければマーケットで評価されてないということではありません。
売却のコツを3つにしぼるなら、
物件の良さを引き出す広告(写真)
売り出すタイミング・季節
不動産会社の言いなりにならない^^;
でしょうか。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
本記事の内容でご不明点などがございましたら、お気軽にお申し付けください。
物件を高く売る方法について、ご興味ございましたら、問い合わせより「興味あり」と、ご連絡ください。担当、田実よりご連絡させていただきます。
不動産はひとつとして同じものはなく、個別性ゆえ売却成功のためには、広く公開し、色々な目的で探している方へ情報を届けることが大切です。
少し癖のある間取りや、特徴ある建物だとしても、あるいは一般的には建物価値がないほど古い建物だとしても、その価値を決めるのは買主であり、その意味で広く公開することが欠かせません。
つまり制限なく情報を公開することが理に適っています。
その点で、インターネットへの掲載は適していて必須の広告です。なかでもsuumoやHOME’Sなどのいわゆるポータルサイトです。
今や不動産(マイホーム)を売却するのに、ポータルサイトへの広告をなしに成功させることはできません。
しかし一方で、売り場でどこでも扱われている物件という見え方をしたら、購入検討者はどう感じるでしょうか。
具体的に、例えばポータルサイトに同じ物件で10社が掲載していて、画面を下へスクロールしても同じ物件が上から下まで並んでいたらどうでしょう。
安売りしてるように感じないでしょうか。少なくとも、希少性があるとは思えないでしょう。
そしてさらに、どれも同じ写真で担当者の顔だけ異なっているみたいな。
ズラッと並んでいれば、インパクトはありますし、見落とすことはないでしょうけれど、なにか売れ残っている物件のようであまり好ましい売り方とは言えません。
不動産物件はふたつとないものですから、ばら撒く広告は、高値で売却する・売却を成功させるという点で、望ましくないというのが弊社の考えです。
まだまだ不動産業界の写真に対する意識は低く、売買物件でもスマホで撮影したものをよく見かけます。
スマホのカメラ機能は広角にも対応し、綺麗に写真を撮れるようになりましたが、やはり一眼など本当のカメラには及びません。
今ではネットで物件を探す方がほとんどであり、画面上の写真の見栄えが反響に大きく影響を及ぼすようになりました。それでは、綺麗な物件写真とはどのようなものでしょうか。
・部屋を広く、水平垂直に撮られている
広角レンズを利用することが必須です。また、下から上に向けたり、反対に高い位置から見下ろすように撮っては、物件の良さが伝わりません。水平垂直に、広角レンズを利用して撮ることです。
状況によっては、室内を撮るのにバルコニーや部屋の外側から撮る工夫もありでしょう。
・部屋全体が明るいこと、窓からの景色も見えること
スマホで部屋を明るく撮ろうとすると、窓の先は真っ白になってしまいます。
部屋を明るくすることと、窓からの景色も見えるように撮ることは、一眼カメラで撮影した後に、専用ソフトで編集する工程が不可欠です。
部屋も明るく、そして窓からの風景も写っている写真を想像してみてください。物件の良さが伝わってくるのがイメージできると思います。
・午前中の撮影
正午を過ぎると、日光が黄色っぽくなり、部屋全体の明るさが半減してしまいます。日差しの差し込むお部屋を表現するには午前の撮影が必須です。
・スマホのタテ画面にも対応
スマホで物件検索される方は90%以上とも言われています。スマホは縦画面ですので、縦に撮影した写真の方がより画面全体に表示されダイナミックに印象が伝わります。
縦写真を意識的に撮影することも大切です。
・スポット撮影も
基本的には広角レンズが活躍しますが、望遠側のレンズを使ってスポット撮影すると、雰囲気のある写真を撮ることができます。
カーテンに日が差し込む柔らかな窓際の表情だったり、お庭のお花や植物の一部だったり、一点にフォーカスした写真もグッと印象がよく伝わります。
今回は以上です。参考になれば嬉しく思います。
(2023年12月時点の情報です。最新情報をお確かめください。)
不動産を売却する場合に利益が出る場合には、5年超所有するものについては約20%、5年未満の場合は約39%の税金(所得税など)がかかってきますが、これまで住んでいた住宅(=居住用財産)の場合は、3,000万円までは利益を控除できるという特例があります。
※所有期間10年超の居住用財産の売却は6,000万円まで約14%
一方で、居住用財産を購入する場合は、よくお聞きになっているかと思いますが、要件を満たす場合に”住宅ローン減税”が利用でき、年末の残高に対する0.7〜1%の所得税が戻ってくる制度があります。
買い替えの場合、売却と購入のその両方について特例を利用することができません。
つまり3,000万円控除と住宅ローン減税のどっちが得かを判断して申請するということになります。
では、どちらが得なのかを前の配信でも例とした2018年に購入した世田谷区のマンションを売却した場合を想定します。
まず、2018年に6,600万円で購入したマンションは、5年後の現在は8,500万円まで価格上昇しています。
※国土交通省から発表される統計情報をもとにしています。
譲渡益(値上がり分)は、概ね1,900万円です。
※説明を平易にするため計算は簡素化します。
本来なら1,900万円に対して、約20%の所得税がかかりますので、380万円の譲渡所得税を払う必要がありますが、3,000万円控除を利用すれば、無税となります。
一方、住宅ローン減税を利用する場合ですが、購入する物件によって異なるので箇条書しますと、
※購入物件は5,000万以上の物件を単独名義で購入するものとする。
※2024年以降に入居するとする。
新築住宅もしくはリノベされた業者売主物件(≒リノベ住宅)・・・A
A-1 長期・低酸素認定住宅の場合の最大控除額は、約409万
A-2 ZEH水準省エネ住宅の場合は 約318万円
A-3 省エネ基準適合住宅の場合は、約273万円
上記以外は、適用なし
中古住宅で一般の売主様から購入する場合・・・B
B-1,2,3の場合は、約210万円
上記以外は、約140万円
となり、A-1以外は、3,000万円控除を利用したほうが得することになります。
新築の建売住宅やリノベマンションを買い替え物件として購入する場合は、売却する物件によっては、住宅ローン控除の方がメリットが出る場合があるという結果になりました。
一方で、中古のリノベされていないマンションを購入する場合では、3,000万円控除の方がメリットが大きいケースが多そうです。
ただし、住宅ローン控除は、債務者1人ずつに適用できますので、例えば夫婦それぞれの共有名義で購入する場合は、フルで適用できる場合は倍になります。
仮に、省エネ住宅でない一般の売主様から購入する中古マンションの場合は、2,000万円が最大限度のため、140万円×2人分=280万円分の税金が戻ってくることになります。
※省エネ基準以上の場合は210万×2=420万
このシミュレーションは事例を平易にした比較です。ケースによって結果は異なってきますのであくまで参考としていただき、実際に検討する場合は専門家へご相談ください。
今回は以上です。このシュミレーションが皆様のお役になれば嬉しく思います。
(2023年12月時点の情報です。最新情報をお確かめください。)
中古マンション価格は、2012年以降上がり続けていることはこれまでのメールでもお伝えしてきました。
今回は、世田谷区内のマンション価格上昇率2012年比(2012年当時と現在の坪単価上昇率比較)について、築年数別で調べてみましたので、ご参考にしていただけたら嬉しく思います。
一般的なマンションを想定し、専有面積は40㎡〜100㎡の取引に限定しています。なお、統計データは国土交通省から4半期ごとに発表される不動産の取引価格情報提供制度「土地総合情報システム」を利用しています。
※2023年12月時点の統計情報を基にします。
築年数を下記3区分に分類しました。
ひとつめは、いわゆる旧耐震物件で1982年築までの築41年以上のマンション-①
次は、1983年〜2002年までに建築された築40年から築21年まで-②
最後は、2003年〜2023年までの築20年以内-③ です。
2012年から現在までの価格上昇率は、
①が、48.3%(坪単価155万から230万へ上昇)
②が、44.0%(〃211万から304万〃)
③が、49.7%(〃249万から373万〃)
という結果になり、築年数に関わらず上昇してきたことがわかります。”旧耐震”だから価格が上昇していないことはないようです。
これは近年のリノベーションブームが影響しているのではないかと思います。リノベーションが普及する前、住宅改装を”リフォーム”としか呼んでいない時代は、リフォームローンは7年程度の短期でしか組むことができませんでした。
そのため、築年の古いマンションは需要が低く、取引価格も落ち着いていたはずです。今ではリノベーション費用が、物件購入と同じように35年ローンで組めるようになったため、改装に大きな費用をかけて自分仕様のマンションにする住まい方が浸透し、結果築古マンションの需要が高まったことが影響していると思います。
また、③の築年幅について、更に10年単位で区分した上昇率についても調べてみたところ、
③-1 2002年〜2012年に建築されたマンション
③-2 2013年〜2023年に〃
とします。
③-1は、40.9%(坪単価249万円から351万円へ上昇)
③-2は、57.0%(〃263万円から414万円〃)
であり、築10年未満の上昇率が特に高く、築後約10年〜20年の物件は、世田谷区全体と比較しても低い結果となりました。
いささかこの結果には驚き、理由も想像できないところではありす。しかしいずれにしても40%超の上昇率ではあります。
採用しているデータは、売却した方へのアンケート結果を基にしているようで、マーケットで取引されたすべてではないことをご承知おきください。
この情報が皆様のお役になれば嬉しく思います。
お持ちの物件を売却検討する場合、今すぐ売らないという選択肢も当然あるはずです。売却せずに賃貸して家賃収入を得るということも不動産運用のひとつの方法です。
売却と賃貸の判断をする基準について掘り下げていくのが今回の目的です。
結論としては、ローンがない場合の例では、27年以降で賃貸が売却益を上回り、5年前に購入した物件でローンがある場合だと、分岐点は72年という結果でした。
詳細は以下の通りです。
まず、前回のメールでも触れましたが2012年以降の東京の不動産価格は大きく上昇しました。一方、売買相場の上昇に対して、家賃相場も上昇しましたが、売買相場と比例するほどには上がらないのが日本の住宅賃貸市場の特徴です。
今の世田谷の賃料と売買相場は、概ね利回りに換算して3.5%〜4.0%程度となっています(賃料が月額25万円の物件の売買価格換算は7,500万円〜8,570万)。
仮に3.7%として(約8100万円)、税金や経費を考慮しないシュミレーションでは、売却額が賃貸収入を超えてくるのは27年以降となります。仮に諸経費率10%、所得税20%として、経費を加味すれば、35年以降でやっと売却金額を超える計算になってきます。
一時賃貸に出して、将来のお子様用にと残しておく選択などもいいですが、利益優先の前提では賃貸は先の長いに話しになってきます。
また、多くの方は住宅ローンを組んでおり、ローンの返済まで考慮すれば、もっと期間がかかることになります。
仮に、5年前に購入したマンションで例にしてみましょう。
2018年に6,600万円で購入したマンションは、6年後の現在は8,500万円まで価格上昇しています。
※国土交通省から発表される統計情報をもとにしています。
※2024年現在
まず賃貸した場合ですが、
期間35年、金利0.5%、借入れ価格6,600万円でローンを組んだ場合の毎月返済額は17.2万円。
管理費・修繕積立金が月額3万円、固定資産税が年額12万円、月額25万円で賃貸した場合の年間の税引前手残り額は45.6万円で、税率20%として約36万円(実際には減価償却があるので、もう少し手残りは多くなります)。
では、売却する場合は、
2023年11月時点でのローン残債は5,580万円で、8,500万円で売却できたとします。
差し引くものとして、まず譲渡益は約1,900万円ですが、居住用財産の3,000万円控除が利用できますので譲渡所得税はゼロ。
売却するのに仲介手数料が約288万円かかり、ローン残5580万円を一括返済した残りは、約2600万円です。
賃貸に出して毎年約36万円、売却したら2600万円となり、賃貸の利益が売却益を超えるには72年かかることになりました。
この結果をどう捉えるべきでしょうか。
まだ今後売買相場が上昇すると考えれば、今は賃貸に出して天井と思うタイミングで売却することも選択肢としてはありでしょう。
ただし、賃貸運用をすれば、住宅用家屋ではなくなってしまうので、3,000万円控除が利用できなくなるのでそれも考慮して決断する必要があります。
また、賃貸で入られた方がいつ出るかはわからず、売りたいときに空室になっているとは限りません。賃貸中のままで売却すれば、相場より安く売らなくてはなりません。
賃貸売買比較は、以上の結果になりました。参考になれば嬉しく思います。