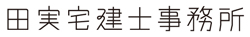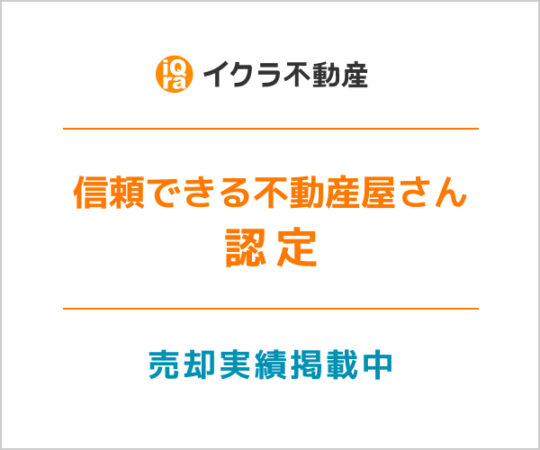前回は、専任媒介は任せっきりにできる一方で、一般媒介では複数の業者とやり取りが必要になる、という違いについてお話ししました。
今回はその続きとして、「なぜ専任媒介に落とし穴があるのか」、その背景と具体例をもとに解説していきます。
■両手仲介と片手仲介
不動産取引では、売主様と買主様の間に、不動産業者が1社だけ介在する場合と、2社以上が介在する場合があります。
1社のみの場合、売主様から依頼を受けた業者が買主も見つけてくるため、仲介手数料を売主・買主の双方から受け取ることができます。
一方で、他社が連れてきた買主と成約した場合、売主様が依頼した業者は売主側の報酬しか受け取れません。
この仕組みから、「自社で買主を見つけたい」という意識が強く働き、他業者の内見を拒むなどの行為が起きることがあります。これがいわゆる「囲い込み」です。
■利益相反であるが一般の売主様が見破ることは困難
囲い込みが行われると、本来より条件の良い買主が排除され、売主様が不利な条件で売却してしまう可能性があります。
こうしたリスクを防ぐ一つの方法が、専任媒介に限定せず、一般媒介も含めた選択を検討することです。
一般媒介にもデメリットはありますが、売却機会が限られる売主様にとっては、「どの契約が自分にとって最適か」を理解したうえで判断することが何より重要です。
季節の写真
 皇居”乾門”の紅葉
皇居”乾門”の紅葉
不動産売却では、まず「どの媒介契約を選ぶか」が大切なポイントです。契約の種類次第で売却の進め方や結果が変わるため、仕組みを知っておくことが重要です。今回は、その基本をわかりやすく整理してご紹介します。
■ポイント1:媒介契約とは“売却を委任する”ための約束ごと
媒介契約とは、売主様が不動産会社に「売却活動をお願いします」と委任するための契約です。業者は売主様の代理として、物件情報の公開や買い手探しを行い、条件の良い購入希望者を見つけてくる役割を担います。本来は“売主様の利益を最大化するための仕組み”ですが、現実にはその役目が十分に果たされていないケースも存在します。
■ポイント2:媒介契約は「一般」「専任」「専属専任」の3種類
売主様が選べる契約形態は、大きく分けて一般・専任・専属専任の3つです。
一般媒介は複数社に同時に依頼できる形で、情報が幅広く共有される一方、やり取りは複数社と行う必要があります。
専任媒介は1社に任せる形式で、窓口が一本化されるため手間が少なく“任せやすい”のが特徴です。(専属専任媒介は今回は割愛)
■ポイント3:「任せきりにできる専任」の裏側
専任媒介では、売主様は1社の担当者にすべてを一任できます。内見の申込みや他社からの買い手情報など、すべての連絡が一本化され、進捗管理がしやすい点がメリットです。しかし、この“任せきりにできる環境”には注意点もあります。実はここに売主様が気づきにくい落とし穴が潜んでおり、詳しくは次回お伝えいたします。
季節の写真
 世田谷八幡宮
世田谷八幡宮
秋らしくなってきました。さて、今回は「売却成功の秘訣は“タイミング戦略”にあり」について、ご紹介します。
<<売却に最適な時期について>>
売買は需要と供給の考え方が大切です。購入者が増える時期に販売時期を合わせるのがセオリーと考えましょう。
■ 購入動機の多くは「ライフイベント」
不動産購入の大きなきっかけは「結婚・出産・進学」です。
特に初めて住宅を購入する層では、その半数以上がこうしたライフイベントを理由に住まい探しを始めます。
新しい生活を迎えるために新居を探すケースは多く、「必要に迫られて購入する」動機が強いのが特徴です。
■ 最も需要が高まるのは1月から3月
「春までには引っ越ししたい」というご家庭が多く、不動産市場は1月から3月に需要が集中します。
進学や入園の前に学区や生活環境を整えたいという背景から、購入ニーズが一気に高まるのです。
この時期に売り出すことで、より多くの検討者に物件を見てもらえ、結果的に売主様に有利な条件での成約につながりやすくなります。
■ 秋から準備、焦らず戦略的に
繁忙期を活かすには、秋までに売却を決め、年内に売却準備を進めておくのが理想的です。
年末年始の広告効果を経て、翌年の需要期に備えることで、売却のチャンスを最大化できます。
また、夏の閑散期あたりに焦って値下げするよりも、時期を見極めてじっくり取り組むことで、満足のいく売却につながる大切なコツです。
季節の写真
 三菱1号館
三菱1号館
お取引後アンケート
私は買主側でしたが、こちらの条件をしっかり理解いただき、売主様と買主の間に立って調整してくださいました。気になる点についても、すぐに現地へ行き確認していただけました。
他社では「とにかく売れればよい」という態度や、適当な情報を流してくるところも見受けられますが、そのようなことは一切なく、真摯にご対応いただきました。
初めての取引で分からないことも多かったのですが、一つひとつ丁寧にご回答くださいました。特に契約書については時間をかけてご説明いただき、取引の流れもきちんと教えてくださったので、安心して決済まで進めることができました。
不動産の取引は金額が大きく、不安や心配も多かったのですが、田実さんのお力添えのおかげで無事に進めることができました。取引そのものだけでなく、税金・保険・建築などさまざまな点が関連してきますが、田実さんは知識・人脈ともに豊富で、全体を通して大変助かりました。
お取引を終えて
このたびは大切なお取引をお任せいただき、誠にありがとうございました。
初めてのご購入でご不安も多かったかと存じますが、安心して進めていただけたとのお言葉を頂戴し、大変嬉しく思っております。
不動産は契約だけでなく、その後の暮らしや資産にも深く関わるものです。今後ともお役に立てるよう、誠実なサポートを心がけてまいります。
お取引後アンケート
売却を任せる業者さんを決めるにあたり、私はまず買い替え先の物件を先に決めました。その際、購入を仲介してくださった業者さんから売却のご提案もいただきましたが、大切な家を手放すにあたっては、やはり何よりも関係性を重視したいと考え、田実さんにお願いすることにいたしました。信頼できる方にご相談したい――それが一番の理由です。
販売金額の設定をはじめ、細やかな気配りや親身なご相談をいただき、大きな安心感がありました。さらに、物件売却にとどまらず、新居の契約に関するご相談やハウスクリーニングの手配まで、多岐にわたりご配慮いただき、お任せして本当に良かったと感じております。
実際の売却価格についても、当初にお伝えしていた希望通りの価格で販売していただき、大変ありがたく思っております。
物件販売について全くの素人で何も分からない中、丁寧に最後まで販売活動していただき、本当に助かりました。素人ならではの相談にも快く応じていただき、心強く感じました。
お取引を終えて
祖師ヶ谷でランドマークとなるマンションをお任せいただきました。人気物件のため販売期間中は常に他の区画が売りに出せれている中での売却でした。使いやすい間取りで、売主様が常にきれいに保っていただいた物件でした。
結果的には、一度の価格改定にとどめご成約の運びとすることができました。誠にありがとうございました。
売却の背景や課題
・子どもが大きくなり、同じ地域内で戸建てに買い替えしたい。
・購入と売却のどちらを先にするか判断がつかない。
・購入先行にすると、安く売ることになるのではないかと心配がある。
売却への道筋
・状況を伺う中で、今回は「購入先行」をご提案し、高値での売却を目指しました。
・買い替え物件の契約条件をアドバイスし、十分な販売活動ができるよう助言させていただきました。
・販売期間中は、高層階の他の販売物件と比較され、問い合わせに苦戦する時期もありましたが、「慌てないことが大切」とアドバイスさせていただきました。
・同じマンション内の販売在庫が減っていく中で、問い合わせの増加に手応えを感じ、価格交渉なくご成約となりました。
・販売開始から約半年後に契約を締結しました。
今年の夏も猛暑ですね。さて、今回は 「相続対策の基礎知識“不動産の相続方法”」 について、ご紹介します。
■不動産を相続する方法
不動産を相続する方法には、現物分割、代償分割、換価分割、共有の4つがあります。それぞれのメリット・デメリットを整理しましょう。
■現物分割
現物分割は、不動産を物理的に分けて相続する方法です。土地を分筆し別々の土地として各相続人が取得できますが、建物を分割できるケースは 極めて少なく、基本的に分割できないと考えてよ いでしょう。
■代償分割
代償分割は、特定の相続人が不動産を取得する代わりに、ほかの相続人に金銭(代償金)を支払う方法です。不動産をそのままの形で活用できますが、不動産を取得する相続人に経済的負担が生じます。
■換価分割
換価分割は、不動産を売却し、 売却代金を分割する方法です。公平にお金を分け られますが、手間や売却利益に対する税金などが 発生します。
■共有
共有は、不動産を物理的に分けずに 相続人全員で共同所有する方法です。不動産を等分して相続でき、各相続人は持分を取得しますが、 将来売却したいと思っても共有者全員の合意が必 要となるため、処分は困難になります。
季節の写真
 咲き始めのシルクジャスミン
咲き始めのシルクジャスミン